私たちが生きている世界には、
身近なことから人類全体に関わることまで、
さまざまな問題が溢れています。
意外に知られていない現状や真相を、
本学が誇る教員たちが興味深い視点から
解き明かします。
アジア太平洋・インド太平洋地域における国際関係や外交問題、特に同盟関係や安全保障協力を中心に研究を進めています。2010年に防衛省防衛研究所に入所して以来、日本とオーストラリアの安全保障協力を主なテーマとしてきましたが、2022年に著書を上梓し、一つの節目を迎えました。今後は、韓国やインドとの安全保障協力や防衛政策にも研究の幅を広げていく考えです。
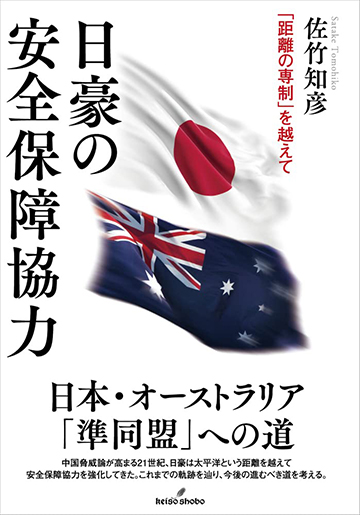
戦後のアジア太平洋地域では、「ハブ・アンド・スポークス」と呼ばれる米国を中心とした二国間の同盟関係が維持されてきました。北大西洋条約機構(NATO)のような集団防衛体制が発展した欧州とは異なり、国家間が海で隔てられ、また国の規模や経済発展の度合い、それに政治体制や価値観の面でも多様な国々の存在するアジア太平洋地域では、アメリカとの「縦のつながり」は維持されても、同盟国同士の「横のつながり」はあまり発展してきませんでした。
ところが、冷戦が終焉すると、米国との同盟関係のみならず、同盟国同士の協力が徐々に発展するようになります。その代表的な例が、日豪の安全保障協力です。今では想像しにくいかもしれませんが、オーストラリアは第二次世界大戦で日本と激しく戦った相手国です。ところが、戦後は経済を中心に関係を深め、さらに冷戦後には安全保障でも距離を縮めてきました。今日、日本とオーストラリアは共にアメリカの緊密な同盟国であり、また自由民主主義的価値観を重視するという共通項があります。オーストラリアのことを、アメリカに次ぐ「準同盟国」と呼ぶ人もいます。
その一方で、日本と韓国の関係は歴史問題などもあり、必ずしも順調ではありませんでした。ところが、近年は北朝鮮の問題や中国の台頭などもあり、日韓の安全保障協力も徐々に進展してきています。このような、同盟国や地域諸国間の「横のつながり」の強化が、今後の地域の安全保障環境にどのような影響を及ぼすのかという点に関心があります。
私が専門とする国際関係論は、これまでアメリカやイギリスなど欧米諸国を中心に発展してきました。日本の安全保障の研究も日米同盟に関するものなどが主流でしたが、今や国際政治経済の重心は、欧米からアジアにシフトしています。また、トランプ政権の台頭などにより、アメリカの地域関与は一層不安定なものになっています。こうした中、日本を含む地域諸国が、水平的な協力を強化しながら地域の安定を維持していくことができるのか――この問いこそが、私の研究における最大の問題意識です。
私が日豪・日韓関係を研究するようになったきっかけは、高校卒業後のオーストラリア語学留学に遡ります。当時、諸外国の留学生と国際問題や互いの国について議論する機会がありましたが、自分の知識不足を痛感し、悔しい思いをしました。この苦い経験が、国際関係分野をめざす原点となったのです。
大学では日本の防衛や外交政策を研究し、修士課程修了後に再び渡豪しました。オーストラリア国立大学大学院では、戦後の日本とオーストラリアの安全保障政策に多くの類似点や共通点があることにも気付き、博士論文では日米同盟と米豪同盟の比較研究を行いました。それ以来、日本とオーストラリアを軸にアジア太平洋地域の国際関係を研究し続けています。

オーストラリア国立大学大学院での学位授与式の写真
もともと研究の道に進んだのは、昔から特定のテーマについて深く考えることが好きだったからです。同じく研究者だった父の影響も少なからずあると思います。仮説を立て、思考を巡らせながら論証する過程は、研究の醍醐味です。既存の枠組みにとらわれず物事を捉え直し、新たな発見に至った瞬間の驚きや達成感が、研究を続ける原動力となっています。
2023年に防衛研究所から本学へと研究の場を移しました。そのように決断した理由はいくつかありますが、最大の動機は、より自由で客観的かつ俯瞰的な視点から研究を進めたいという思いでした。また研究所時代に、自衛隊基地の研修や各国政府の高官と交流したり、防衛省職員や自衛官の方達と直接議論を交わす機会も多く、そうした経験を通じて得られた安全保障の「生の現場」についての知見をより広く社会一般に広めていきたいと思ったこともあります。大学に移り、学生と意見を交わしながら議論を深めていく時間にも、大きな魅力を感じるようになりました。現在は、これまでの実務経験を生かして事例を交えた講義や学生と共に政策シミュレーションを行うなど、双方向的な授業を心がけています。安全保障を専門に教える授業はまだ少ないので、学生たちは目を輝かせながら講義に耳を傾け、理解を深めているように感じられます。そうした姿に刺激を受けながら、アクティブラーニングの要素を意識的に取り入れ、教育にも力を注いでいます。
大学時代の恩師の言葉で印象に残っているのは、研究テーマについて「世界の誰よりも知るつもりで調べなさい」という言葉です。研究と聞くと、成果や結果にばかり目が向きがちですが、実際の作業の多くは、未発掘の資料を探し出したり、シンクタンクの膨大な文書を読み込んだりといった、非常に地道な作業です。また私が扱っているのは現代の政策課題も多いため、実務経験者に対するインタビューの機会も多くあります。大臣経験者や元外務次官といった要人でも、快く話を聞かせてくださることも多く、現場の声を直接知る貴重な機会となっています。
研究を進めるうえで私が大切にしているのは、俯瞰的な「鳥の目」と、現場に寄り添う「虫の目」の両方を持つことです。抽象的な議論や概念に偏りすぎると、複雑さに満ちた現実社会を説明することはできませんし、逆に細かい事実に拘泥すると、その背景に潜むより大きな構図を見逃すことになります。「真理は細部に宿る」をモットーに、なるべく丁寧に事象を追いながらも、大きな視点を忘れないことを意識しています。また、一国の立場にとらわれず常に異なる視点に立って物事を考えること、多様な要因を総合的に捉えて複眼的に理解する姿勢も重要です。研究の世界では、「Counter-Intuitive」、つまり世の中の直観に反する、常識を覆すような研究成果にこそ価値があるとも言われます。そして、これは大学の学びにも通底します。
国際関係を学ぶ皆さんには、ぜひ海外留学を体験してほしいと思います。私自身も、留学中は言語の問題や生活環境の違いに苦労しましたが、同時に多様な価値観を学び、人生観を大きく変える契機となりました。特に安全保障分野では、日本はまだ「ガラパゴス化」しているのが現状です。国際関係を俯瞰して、日本の立ち位置や戦略を正しく把握するには、海外からの視点が欠かせません。アジア地域を深く理解するために、オーストラリアや韓国、さらにはインドやインドネシアといった国々への留学も視野に入れるとよいでしょう。
大学は、受け身で知識を得る場ではなく、自ら主体的に学びに向き合う場です。動かなければ何も得られません。通俗的な理解や「世間の常識」にとらわれず、自由な発想を持ちながら知的好奇心を原動力に、貪欲に学びを深めてください。また、さまざまな情報があふれる現代社会においては、批判的思考や正しい情報を見極める姿勢を養うことも重要です。授業ではAIやChatGPTを活用する機会もありますが、大切なのはいかに情報を解釈し、応用するかという点です。そうした意識が「自ら考える力」につながります。高い志をもって挑戦し続ける学生たちに寄り添いその成長を支える存在であるために、今後も努力を続けていきたいと思っています。

ゼミ合宿で訪れた韓国の延世大学での集合写真